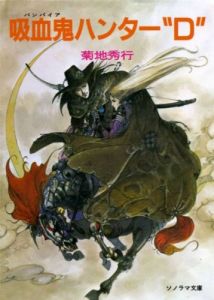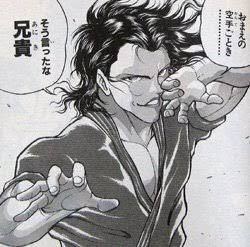厳密に言えば2周じゃなかった
7話から観たから
7、8、9と連続でシリアス展開だったからはい、こんばんみ
伊之助ですよ
ぼく、明日徹夜>>950
犬の飼い方ですよ
色々飼ったが犬だけない
モルモット、ウサギ、ニワトリ、鯉、亀、ねこ、熱帯魚
ハム太郎
なんで犬だけなかったかな?って言うか東、ラルに払い下げで良いのか?
キノコ生えてるんじゃないの?
大四畳半に?>>939
月曜日だからね
まぁ土日で…
抜くもん抜いたんでしょ>>962
まぁビミョーだけれどなぁ下ネタwww
天野…
天野ナントカ
忘れた
流行ったよね
刃牙の初期もあんな感じ
絵はそれで台詞は夢枕キャラ的に天野絵と夢枕の具現化って鎬弟よね
目立たんけど 笑>>976
デビルマン臭っ!キマイラは完全に終わらない気がしますねww
>>979
あれさぁ…
まぁ読んでたけど…
なんかストイック言うかM言うか…
とちうで色気づいて辞めた 笑就職してからあんまり読まなくなっちゃった
そんなもんだろうね
時折発作起こして池波読んだけどやっぱ掴みのある
梅安、鬼平、秋山親子だもの
なかなか新規には
だから偉いと思うよ ジャンル固定しない人>>990
いやもう今でも続いてるならホントに出だしだけだから
読んだの
仲間増えてるの?
ジャンプノリって? トーナメントとか?笑
ま、あとでね
着いた>>991
鬼平は時代劇のブラックジャックと捉えていいのかな?
1話完結ですし>>997
ってかそれしか読んどらん 笑
道徳過ぎて辞めた
色気づいて>>996
一歩とかキングダムとか無闇に長いのは苦手なんですよね
とかいいつつグインサーガは120巻読みましたけどねww
読書感想スレ
1000
ツイートLINEお気に入り 981
981 6
6
レス数が1000を超えているためこのスレッドには書き込めません